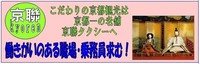2013年01月30日
国立博物館ならではの迫力の宝物群 初公開の名品も必見!
 十二天像のうち毘沙門天 (京都国立博物館所蔵)
十二天像のうち毘沙門天 (京都国立博物館所蔵)特別展観 国宝 十二天像と密教法会の世界
承和元年(834)、空海は、仁明天皇の許しを得て、後七日御修法を始めました。正月七日まで行われる宮中節会の後に引き続いて七日間行われるため、この名があります。宮中に真言院という専用の道場を置き、天皇の安泰と国家の鎮護を祈る修法で、真言宗単独で行われました。その後、一時的な中断はありましたが、現在でも場所を東寺の灌頂院に移し、勅使の臨行をあおいで連綿と続けられています。
当館には、大治二年(1127)に後七日御修法のため新調された十二天像が完全セットで所蔵されています。今回、この国宝 十二天像を一堂に展示し、関連遺品をまじえて後七日御修法を紹介します。
また、当館のもう一つの名品、国宝 山水屏風は、灌頂という密教の教えを伝える重要な儀式で十二天屏風と共に用いられてきました。他の遺品とあわせて灌頂の歴史も紹介します。これら真言宗の二大重要法会を軸に深遠な密教文化の一端に触れて頂ければと存じます。
 十二天屏風のうち(神護寺所蔵)
十二天屏風のうち(神護寺所蔵)特 集 陳 列 成立八〇〇年記念 方丈記
「ゆく河のながれは絶えずして、しかももとの水にあらず(原文、漢字片仮名交じり)」で始まる『方丈記』は、鴨長明(1155?―1216)が建暦二年(1212)三月に執筆したもので、わが国を代表する随筆として知られており、本年(2012)には成立八百年という大きな節目を迎えました。この『方丈記』は、世の中の無常を表現したことで有名ではありますが、京の都を襲った五大災厄なども回想しており、近年ことに災害史のうえからも注目を集めている随筆でもあります。
歌人でもある鴨長明は、下鴨神社(賀茂御祖神社)の正禰宜惣官、長継の子。建仁元年(1201)四十七歳の時に和歌所の寄人となりましたが、五十歳の時に出家して大原に籠り、のち日野の外山に移り、方丈の庵を結んで隠棲し、著作に従いました。
今回の展示では、自筆本という伝承がある最古の写本、大福光寺本(重文)を中心に、関連する資料および同時代の漢字片仮名交じり文の書跡などを合わせて展示します。(京都国立博物館)
会 場 京都国立博物館 特別展示館 1~10室
〒605-0931 京都市東山区茶屋町527
http://www.kyohaku.go.jp/
TEL 075-525-2473(テレホンサービス)
会 期 平成25(2013)年1月8日(火)~2月11日(月・祝)
休 館 日 月曜日
*ただし1月14日、2月11日は開館、1月15日は休館
観 覧 料 一般 1,000円(800円) *( )は団体20名以上
大学・高校生 700円(500円)
中学・小学生 無料
*本料金で特別展観「国宝 十二天像と密教法会の世界」及び特集陳列 成立八〇〇年記念「方丈記」をご覧いただけます。
開館時間 午前9時30分~午後6時(毎週金曜日は午後8時まで)
※入館は閉館の30分前まで
***平常展示館は、建替え工事のため閉館しております***
Posted by 京聯自動車観光部 篠田ほつう at 15:28│Comments(0)
│京の歳時記・あたりまえ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。