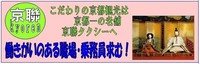2013年03月30日
2013年03月30日
本法寺

時の将軍足利義教に「世の乱れ……」を説き、酷刑を受け、後に「鍋かぶり日親」と称された日親上人が本阿弥家の帰依を受け創建したとされる本法寺、今年の直木賞受賞作「等伯」でも話題になった長谷川等伯ゆかりの寺でもあります。ここも少しずつ知られてきていますが、まだゆっくり見事な桜が鑑賞できます。http://www.kyoren-cab.jp/
2013年03月30日
2013年03月30日
2013年03月29日
2013年03月29日
2013年03月29日
2013年03月29日
2013年03月29日
2013年03月29日
2013年03月29日
伏見戦跡に咲く桜並木

京橋といっても大阪ではありません。京都の伏見にあります。かつて京と大坂を結び、三十石船など、千を超えると言われる船運で賑わった伏見港の中心がこの京橋周辺でした。角倉了以の高瀬川開削で、京と伏見が結ばれるとさらに賑わいを呈します。江戸期には、大名の本陣、家臣のための脇本陣や旅籠が軒を連ねていました。
幕末の鳥羽伏見の戦いでは、新政府軍と、旧幕府軍の間で激しい戦闘が行われたのもこのあたりです。案内板には「……鳥羽伏見の戦いが始まる前日夕刻、会津藩の先鋒隊約200名が大坂から船で伏見京橋に上陸。ここ伏見御堂を宿陣として戦った。伏見奉行所に陣を置いた幕府軍や新選組が民家に火を放ちながら淀方面に敗走したので、このあたりの多くの民家が焼かれ、大きな被害を受けた……」とあります。
京橋の袂、豊臣秀吉の伏見城築城の際に、外堀として開削された濠川に沿って咲く桜並木が、今年も朝日に美しく映える季節がやってきました。

2013年03月25日
2013年03月25日
2013年03月24日
2013京の桜咲く 祇園白川満開

大和大路通から辰巳大明神を結ぶ白川南通のしだれ桜が満開です。周囲の外観とマッチしてグッド。祇園白川は、情緒ある町屋が並び、祇園町の昔の風情を今に伝える一角です。
芸舞妓さんたちがしゃなりしゃなりと歩いて来て、芸事の神様とされる辰己大明神に手を合わせる。火曜サスペンス劇場などでもお馴染みの光景ですよね。ところでこの神社、京都御所の辰巳(南東)にあることから、この名があるのですが、辰己稲荷と言われたりするので、お狐さんを祀ってあると思われがちですよね。でも実は祭神は狸だって知ってました?。
昔、巽橋にいたずらな狸が棲んでいて、橋を渡ろうとする人を化かしては川の方を渡らせるので、この界隈の者たちが、祠を建てお狸さんを祀ると、いたずらは治まったというんですね。
しだれ桜の覆いかかる石碑は、東京の伯爵家の出ながら、京を愛し、都おどりの復興など祇園の復興に尽力した歌人として知られる吉井勇の歌碑です。「かにかくに祇園はこひし寝るときも枕の下を水のながるる」と彫られています。

2013年03月21日
梅と桜が一緒に楽しめますよ!
車折神社は、平安時代の建立当初より境内には桜が咲き誇り、「桜の宮」と呼ばれていました。後嵯峨天皇が大堰川に行幸したとき、牛車の轅(ながえ、前方の長い棒)が突然折れたので、不思議に思って尋ねると、清原頼業公を祀るというので、後に「車折大明神」の神号と正一位の神階を贈ったため、以後「車折神社」と呼ばれるようになったといいます。「約束を違えないこと」をお守り下さる霊験あらたかな神様です。
昨日境内では、日本近代画の巨匠、冨田溪仙が献納した溪仙桜が、この陽気で一気に開花しました。ここでは昨今、梅と桜の競艶も楽しめます、そういえば京都は、桜が昔より早く、梅が遅くなってきていますものね。
またここには、芸能、芸術の神様とされる天宇受売命(あめのうずめのみこと)を奉る芸能神社があります。
この神様、何故芸能の神様かというと、天照大御神が天の岩戸にこもってしまって、この世が暗闇になった時、岩戸の前で大いに演舞して、大御神を再び出現させ、この世は再び光を取り戻したとの伝承からきています。実は裸踊りだったとも言われていますけど……。
そういうわけで、境内中が参拝した芸能人たちの奉納した玉垣で囲われています。ちなみに里見浩太朗さんや内藤剛志さん、雛形あきこさん、中村玉緒さんからEXILEやAKB48にBerryz工房といった人たちまで、実にたくさん、圧巻です。
2013年03月13日
怖いくらいのド迫力 80体の星神たち

大将軍とは、陰陽道(古代中国の道教の影響)において方位の吉凶を司る神様です。
かつて日の本の都は、皇位継承に関わる血みどろの政争に明け暮れた平城京から長岡京へ遷都しましたが、長岡京でも骨肉の政争は収まらず、十年後にはさらに平安京へと遷都がなされました。
時の朝廷は新たな都を最澄、空海を始めとする密教や陰陽道に基づいて包囲網を形成して王城鎮護しようとしたと言われます。何故なら、当時の人々、とりわけ為政者たちは、「不幸の続く元凶はかつての政争で追いやった者たちの怨霊のなせる業」だと信じていたからでもありました。病気・地震・旱魃・雷・洪水などの災害もまたしかりです。
桓武天皇は、北に山(玄武)・船岡山、東に川(青龍)・鴨川、南に池(朱雀)・巨椋池、西に道(白虎)・山陰道と四神相応の土地を選択すると同時に、鬼門、裏鬼門を寺社仏閣で固め、さらには大将軍を祭神とする4つの大将軍神社を四方に置いたのです。
平安時代に大内裏(御所)の北西角の天門に星神 「大将軍堂」を建て 方位の厄災を解除する社として創建されたのが大将軍八神社です。場所を移すことなく千年以上、方位を司る神様としてあがめられてきました。
平安時代の今様には、祗園(八坂神社)、日吉(日吉大社)、賀茂社(上賀茂・下鴨神社)とともに霊験あらたかな神として歌われるほどの社だったといいます。平家一門が清盛の娘・建礼門院 の安産祈願に訪れた場所でもあります。
方徳殿(収蔵庫)には、神像80体(内79体が重要文化財)がずらっと居並び睨みを聞かせます。神像の視線は部屋の中央に集まるような配置になっていて、その壮観な姿は、大将軍信仰が最も盛んだった平安中期から鎌倉末期にかけて制作された神像たちです。
実は、密教や陰陽道の宇宙観をあらわす「星曼荼羅」の世界を、星を司る神像を並べて立体的に表現した「立体星曼荼羅」なのです。これだけの数の神像が一箇所にまとまって伝わっているのは日本でここだけです。

また、陰陽道安倍家の古天文暦道資料(府文)があり、江戸時代の天文学者・渋川春海の天球儀が残されています。
天球儀とは、天空を球面に見立て、星、星座、赤道などを描いたもの。大将軍八神社にある木製の天球儀は、江戸時代につくられたもので、星の数は全部で1763あるといいます。現在日本に残る天球儀では最も古いもののひとつです(伊勢神宮にも同時期の作があります)。
作者は、この秋の映画にもなった、沖方汀さんのベストセラー小説『天地明察』の主人公で天文学者の渋川春海(しぶかわしゅんかい)です。
初めて国産の「貞享暦」という暦を作った人ですね。日本では奈良時代に唐からもたらされた暦が使われていました。しかし、安土、桃山時代にもなると、中国と日本では場所が離れていることもあり、日食や月食も予測できなくなるなど不具合が生じてきていたのです。
春海はマテオ・リッチの世界地図を確認しながら天体観測し、中国と京都間の距離を計算し、日本に合った国産の暦を作成しました。
もう一人、春海とともに日本初の国産暦の作成に尽力した人物がいます。陰陽師・安倍晴明の子孫、土御門秦福でした。土御門家は朝廷の「陰陽頭」として、賀茂家と派を競う、陰陽道・天文学・暦の第一人者でした。明治維新後、土御門家も東京へ移った際、陰陽道安倍家の古天文暦道資料(京都府指定文化財)が、大将軍八神社に大量に引き継がれました。
徳川幕府八代将軍吉宗による禁書政策の緩和により、西洋の資料を日本で閲覧できるようになります。その際、西洋から輸入されたアルファベット表記の天文図をはじめ、貴重な資料が展示されています。

2013年03月03日
平安雅鮮やかに ひいなまつり
市比売神社で「ひいなまつり」がありました。「ひな」は「小さくてかわいらしいもの」の意で、「ひな」の古語が「ひいな」なのだそうです。身代り信仰で、古代より人形(ひとがた)が人間の身代わりに厄を引き受けてくれると考えられてきたことに由来します。
上巳の節句(桃の節句)の厄払いに、はじめは「流しびな」、そのうち「雛遊び」が盛んになり、やがて「雛人形」を飾るようになります。娘の厄を受けるひな人形はその家の財力の象徴として華やかさを増してゆき、立派な雛人形を飾るようにとなっていきます。女の子が生まれると、親たちは娘にひな人形を与えて初節句を祝うことで、娘の身代わりに人形に厄を背負ってもらい、健やかな成長と幸せな人生を願いました。
雛人形を自慢する「ひな合わせ」や、ご馳走を持って親戚を訪ねる「ひなの使い」、「ひなの国見せ」などが流行ったのだとか。
ところでこの市比売神社さんは、「平安京創建後すぐに、京都の左右両市場の守護神として、左大臣藤原冬嗣が堀川の西に勧請した社で、天正年間、豊臣秀吉の京都大改造で現在地に移転された」という由緒ある神社なのですが、なんと今はマンションの一階が神社という珍しいお社です。祭神が全て女神であることから、女性の守り神とされてきました。
ひいなまつりでは、貝合わせなどの平安時代の遊びや衣紋(衣冠・十二単)の着付け方法の紹介や、人が扮する人雛、五人囃子の雅楽、三人官女の舞など、雅やかな公家社会が再現されていました。