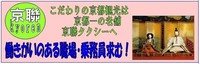2015年05月22日
新緑の草庵
奥嵯峨の竹林の中にひっそりとした佇まい、祇王寺の新緑がまばゆいばかりの風景を醸し出しています。青もみじと敷き詰められた苔のコントラスト、これだけの庭は他では見られません。
祇王寺は、京通の間では、平家物語に登場する悲恋の尼寺として、世の女性たちにも人気の草庵です。
物語は、数年前の大河ドラマでは描かれませんでしたが、「平家物語」に収められている逸話です。
平安末期、平家全盛のころ、京の都で評判の祇王・祇女という白拍子がいました。白拍子とは、今様(流行歌)の踊り手のこと。平清盛は姉の祇王を見染め寵愛しましたので、妹の祇女も世にもてはやされ、母の刀自も立派な家屋に住まわせてもらえるようになり一家は富み栄えます。
ところが、数年後、仏御前という若い白拍子が「舞をみてほしい」と言って清盛の前に現れるのです。最初は「追い返せ」と会おうとしなかった清盛でしたが、「ご覧になられては」との祇王の勧めにより舞を躍らせます。
皮肉なことに、その後、清盛は仏御前に心変わりをしてしまいます。そして、ついには、仏御前を寵愛するあまり、祇王を都から追い出してしましました。
悲しみにくれる祇王と、妹の祇女と母の刀自が隠棲した地、往生院のあったところが、この祇王寺です。のちには、仏御前もまた、「私の罪を許してください。もし許されるなら、一緒に念仏を唱えて極楽浄土の同じ蓮の上に生まれましょう」と祇王を追いかけ、この寺で出家しました。その後、四人は仲良く、念仏三昧の生涯を送ったのだとか。
さて、ここまでは、一般的なお話、やはり少しこだわってみましょうか。
物語では清盛と周りの平家一門が随分と極悪非道の傲慢な人物として描かれています。現代でも、清盛のイメージは良くないようです。しかし、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、奢れるものは久しからず」で始まる「平家物語」は、作者不詳ですが、源氏の世の中になったのち、おそらくは源氏側の有識者によって書かれ、琵琶法師によって、各地に伝えられたと言われています。
最近の研究では、平清盛と平家については、階層にこだわらず交易に目を向けた点など、再評価がされてきています。やはり時の為政者にとって都合の悪い歴史は書き換えられているということでしょうか。ですからこの悲恋物語もまた、そのまま鵜呑みにするわけにはいかないのかもしれませんね!
本堂にある仏壇には、本尊大日如来、祇王、祇女、母刀自、仏御前、そして平清盛の木像が安置されています。祗王、祇女の像は鎌倉末期の作で、作者は不詳ですが目が水晶で鎌倉時代の特徴をよく表しています。(篠)

祇王寺は、京通の間では、平家物語に登場する悲恋の尼寺として、世の女性たちにも人気の草庵です。
物語は、数年前の大河ドラマでは描かれませんでしたが、「平家物語」に収められている逸話です。
平安末期、平家全盛のころ、京の都で評判の祇王・祇女という白拍子がいました。白拍子とは、今様(流行歌)の踊り手のこと。平清盛は姉の祇王を見染め寵愛しましたので、妹の祇女も世にもてはやされ、母の刀自も立派な家屋に住まわせてもらえるようになり一家は富み栄えます。
ところが、数年後、仏御前という若い白拍子が「舞をみてほしい」と言って清盛の前に現れるのです。最初は「追い返せ」と会おうとしなかった清盛でしたが、「ご覧になられては」との祇王の勧めにより舞を躍らせます。
皮肉なことに、その後、清盛は仏御前に心変わりをしてしまいます。そして、ついには、仏御前を寵愛するあまり、祇王を都から追い出してしましました。
悲しみにくれる祇王と、妹の祇女と母の刀自が隠棲した地、往生院のあったところが、この祇王寺です。のちには、仏御前もまた、「私の罪を許してください。もし許されるなら、一緒に念仏を唱えて極楽浄土の同じ蓮の上に生まれましょう」と祇王を追いかけ、この寺で出家しました。その後、四人は仲良く、念仏三昧の生涯を送ったのだとか。
さて、ここまでは、一般的なお話、やはり少しこだわってみましょうか。
物語では清盛と周りの平家一門が随分と極悪非道の傲慢な人物として描かれています。現代でも、清盛のイメージは良くないようです。しかし、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、奢れるものは久しからず」で始まる「平家物語」は、作者不詳ですが、源氏の世の中になったのち、おそらくは源氏側の有識者によって書かれ、琵琶法師によって、各地に伝えられたと言われています。
最近の研究では、平清盛と平家については、階層にこだわらず交易に目を向けた点など、再評価がされてきています。やはり時の為政者にとって都合の悪い歴史は書き換えられているということでしょうか。ですからこの悲恋物語もまた、そのまま鵜呑みにするわけにはいかないのかもしれませんね!
本堂にある仏壇には、本尊大日如来、祇王、祇女、母刀自、仏御前、そして平清盛の木像が安置されています。祗王、祇女の像は鎌倉末期の作で、作者は不詳ですが目が水晶で鎌倉時代の特徴をよく表しています。(篠)

Posted by 京聯自動車観光部 篠田ほつう at 10:37│Comments(0)
│京の四季
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。