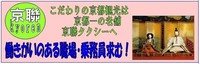2012年04月21日
王朝風造りの寺院をご存知ですか!
大覚寺は876年、第52代嵯峨天皇の離宮を寺院にしたもので、お寺というより宮殿としての特色が各所で見られます。
「村雨の廊下」(天井が低いのは刀を振り上げない、廊下はウグイス張り、侵入者を防ぐため)と呼ばれる細長い回廊によって、各建物と結ばれています。
まるで王朝の優雅な離宮といっても良いでしょう。
また大覚寺は般若心経の寺として特に有名です。普通、真言宗の寺院の本尊は大日如来ですが、嵯峨天皇及び、歴代天皇の写経による心経が本尊として、宸殿前にある心経殿に納められています。
心経殿は奈良法隆寺の夢殿を模して作られた八角形の形をしています。
なお、宸殿前にあるのは左近の梅、右近の橘です。これは古式によるもので、現在各寺社に見られる左近の桜、右近の橘は第54代の仁明天皇によって形式が代えられたものです。
お客様をを案内のとき、平安初期王朝風の造りの寺院として説明させていただいています。

「村雨の廊下」(天井が低いのは刀を振り上げない、廊下はウグイス張り、侵入者を防ぐため)と呼ばれる細長い回廊によって、各建物と結ばれています。
まるで王朝の優雅な離宮といっても良いでしょう。
また大覚寺は般若心経の寺として特に有名です。普通、真言宗の寺院の本尊は大日如来ですが、嵯峨天皇及び、歴代天皇の写経による心経が本尊として、宸殿前にある心経殿に納められています。
心経殿は奈良法隆寺の夢殿を模して作られた八角形の形をしています。
なお、宸殿前にあるのは左近の梅、右近の橘です。これは古式によるもので、現在各寺社に見られる左近の桜、右近の橘は第54代の仁明天皇によって形式が代えられたものです。
お客様をを案内のとき、平安初期王朝風の造りの寺院として説明させていただいています。

2012年02月24日
観音樣は何故崖の上におわします
ふじもんさんの京の旅をもっと楽しゅうする話

清水寺は東山三十六峰の一つ、音羽山の中腹に位置し、両国三十三ヶ所霊場の第十六番札所になります。
奈良時代の末(七七八年)に僧・延鎮が坂上田村麻呂の助力で建立し、宗派は、奈良仏教の一宗である法相宗から独立し、北法相宗と成ります。
ご本尊の十一面千手観音像は、清水型の観音様と呼ばれ、一文字の手を頭上に掲げ、化仏を頂く珍しいお姿をしています。本尊は三十三年毎の御開帳をする秘仏で、観音三十三変化によります。
全ての観音の中で十一面観音は拝んだ時から御利益が与えられています。
観音菩薩は南海にあると云われる補陀落山の崖上で修業中で、古来観音が本尊の古寺は滋賀の石山寺、奈良の長谷寺なども崖上に本尊があります。
観音樣を拝むときは、南無観世音菩薩樣と云って拝んでください。御利益がありますよ。

清水寺は東山三十六峰の一つ、音羽山の中腹に位置し、両国三十三ヶ所霊場の第十六番札所になります。
奈良時代の末(七七八年)に僧・延鎮が坂上田村麻呂の助力で建立し、宗派は、奈良仏教の一宗である法相宗から独立し、北法相宗と成ります。
ご本尊の十一面千手観音像は、清水型の観音様と呼ばれ、一文字の手を頭上に掲げ、化仏を頂く珍しいお姿をしています。本尊は三十三年毎の御開帳をする秘仏で、観音三十三変化によります。
全ての観音の中で十一面観音は拝んだ時から御利益が与えられています。
観音菩薩は南海にあると云われる補陀落山の崖上で修業中で、古来観音が本尊の古寺は滋賀の石山寺、奈良の長谷寺なども崖上に本尊があります。
観音樣を拝むときは、南無観世音菩薩樣と云って拝んでください。御利益がありますよ。
2012年02月14日
ふじもんさんの京の旅をもっと楽しゅうする話
今年は竜年です、蟠竜ではなく雲竜に成る様に努力したいものですね。
蟠竜と雲竜のちがい
今回は蟠竜と雲竜のちがいについてお話します。
雲竜は空を飛んでいる竜。必ず雲が描いてあって、悟りをひらいています。
一方、蟠竜はとぐろを巻き、地面にうずくまって、まだ天に昇らない地上にいる竜です。
龍は仏の教えをたすける八部衆の一つで龍神と呼ばれます。そのため多くの本山では、住職が上がって仏法を大衆に説く法堂(はっとう)の天井に龍 が描かれ、それが法の雨(仏法の教え)を降らすという意味や、龍神が水を司る神であるため、火災から護るという意味 がこめられるのです。
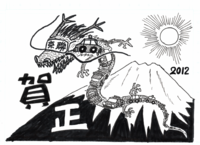 京都で龍の見える寺社をめぐる旅
京都で龍の見える寺社をめぐる旅
天龍寺法堂(雲龍 加山又造) 妙心寺法堂(雲龍 狩野探幽)
大徳寺法堂(雲龍 狩野探幽) 相国寺法堂(蟠龍 狩野光信)
南禅寺法堂(雲龍 今尾景年) 建仁寺法堂(双龍 小泉淳作)
東福寺本堂(蒼龍 堂本印象) 瀧尾神社 全長8メートルの木彫り龍
京聯自動車(株)の新しいホームページを開設しました。観光案内や京の話題もたくさん載ってます。ぜひご覧ください。
http://www.kyoren-cab.jp/
蟠竜と雲竜のちがい
今回は蟠竜と雲竜のちがいについてお話します。
雲竜は空を飛んでいる竜。必ず雲が描いてあって、悟りをひらいています。
一方、蟠竜はとぐろを巻き、地面にうずくまって、まだ天に昇らない地上にいる竜です。
龍は仏の教えをたすける八部衆の一つで龍神と呼ばれます。そのため多くの本山では、住職が上がって仏法を大衆に説く法堂(はっとう)の天井に龍 が描かれ、それが法の雨(仏法の教え)を降らすという意味や、龍神が水を司る神であるため、火災から護るという意味 がこめられるのです。
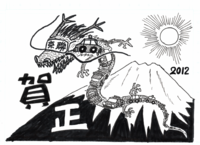 京都で龍の見える寺社をめぐる旅
京都で龍の見える寺社をめぐる旅天龍寺法堂(雲龍 加山又造) 妙心寺法堂(雲龍 狩野探幽)
大徳寺法堂(雲龍 狩野探幽) 相国寺法堂(蟠龍 狩野光信)
南禅寺法堂(雲龍 今尾景年) 建仁寺法堂(双龍 小泉淳作)
東福寺本堂(蒼龍 堂本印象) 瀧尾神社 全長8メートルの木彫り龍
京聯自動車(株)の新しいホームページを開設しました。観光案内や京の話題もたくさん載ってます。ぜひご覧ください。
http://www.kyoren-cab.jp/