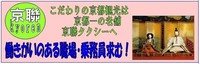2012年10月26日
古都の時代絵巻鮮やかに
10月22日、快晴で真夏日よりの中、時代祭が行われました。明治、幕末、江戸時代、戦国、室町時代、平安時代と其々の装束に身を包んだ艶やかな人々が京都御所を出発。御池どおりから三条、平安神宮へとねり歩きました。
京都の三大祭りの中で、其々の時代衣装が観覧できるので私は、この祭りが大好きです。
2012年10月25日
野宮神社で斎宮行列

「斎宮(斎王)」とは、天皇が新たに即位 するごとに、天照大神の御杖代(みつえしろ)と して伊勢神宮に遣わされた斎王(未婚の内親王もしくは女王)のこと。
斎王が任命を受け、都から伊勢の斎宮へと向う「斎王群行」は、斎王以下監送使、官人・女官などあわせて数百人にも及びました。艶やかな衣装に身を包んだ人々が、当時の様子を再現して、嵐山を練り歩きました。(小丸)
2012年10月16日
釣り大会で大人も子供も大はしゃぎ!
恒例の釣り大会が行われました。場所は、今何かと話題の? 福井県大飯郡大飯町でした。
晴天の中、京聯釣りクラブの匠を中心に三十数名が、大物を狙って凌ぎを削りました。
さて、大物賞は50センチを超える「ダツ」を釣り上げた山田さん、おしい、わずか数センチの差で、中川さんの釣り上げた同じ「ダツ」が二位となりました。
途中、泉さんが仕掛けた竿が目を離した隙に海に持っていかれるハプニングも。引き上げてみると、なんじゃこの珍魚は? 大きな「エソ」がかかっていました。かまぼこに変身する魚だそうで、「う〜ん、どんな味がするんだろうなあ」
なかには100匹近い「アジ」を釣り上げた人もいました。全体的に小振りでしたが、釣り足は大変良く、みんな上機嫌、炊き出しの焼きそばやおにぎりにフランクフルト、新鮮な油であげた捕れたてアジのから揚げなどもおいしくいただいて、楽しい一日を過ごしました。
2012年10月10日
祇園祭の先駆け・粟田祭

粟田祭(粟田神社大祭)
粟田神社の主祭神は、スサノオノミコト・オオナムチノミコトです。古来より厄除け・病除けの神と崇敬されています。
京都の東の出入口である粟田口に鎮座するので、東山道・東海道を行き来する人々が道中の無事を感謝して参拝したことから、いつしか旅立ち守護・旅行安全の神として知られるようになりました。
粟田祭は粟田神社で10月に行われる祭礼行事です。一千年の歴史を持ち、祭には神輿に先行して剣鉾が巡行します。剣鉾は祇園祭の山鉾の原形と云われており、 室町時代には祇園会が行われない際は粟田祭をもって御霊会としたと伝えられています。
一説には奈良朝より活躍した粟田氏の氏神として創建された社とも云いいます。
体育の日前日の「出御祭(おいでまつり)」「夜渡り神事」、体育の日の「神幸祭(しんこうさい)」「還幸祭」、そして15日の「例大祭」までの神事・行事を総称して粟田祭(粟田神社大祭)と呼んでいます。

粟田大燈呂
平成20年の夜渡り神事に「粟田大燈呂」が復興しました。この大燈呂とは文字通り大きな灯篭の山車のこと。戦国の世に公卿の山科言継卿が書き綴った『言継卿記』には、「粟田口の風流が吉田へ罷り向かうということを聞きましたので、夕方に吉田へ罷り向かいました。大きな灯呂が二十あり、その大きさはおよそ二間(3.6メートル)四方もあり、前代未聞のことで大変驚いた」(訳粟田神社)とあります。
この灯篭の出し物がどのようなものであったかは分かりませんが、京都造形芸術大学の協力もあり、時代に則した形で復興することになったといいます。

神幸祭
神幸祭とは神様が氏子区域を巡行され、氏子にお力をお与えになる神事です。神幸祭には、剣鉾が鉾差しによって五〜六基差され、神輿が氏子町内を渡御しています。
剣鉾とは祭礼の神輿渡御の先導を勤め、神様のお渡りになる道筋を祓い清め、悪霊を鎮める祭具です。剣先は真鍮の鋼で造られ、額には御神号や神社名・年号などが記されています。
氏子区域には現在18基計44本の剣鉾があり、京都で最も多くの剣鉾が備えられています。剣鉾は講中(鉾仲間)又は町中(鉾町)で守護されており、現在もその形式は変らなく守られています。