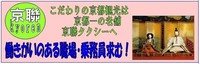2013年06月29日
大徳寺
大徳寺

大徳寺は、ご存知、臨済宗大徳寺派大本山です。山号を龍寶山(りゅうほうざん)といい、本尊は釈迦如来、鎌倉時代末期に大燈国師・宗峰妙超が開創しました。宗峰妙超は悟りを開いたあと20年間も五条河原で乞食行を続けたといいます。
花園天皇、後醍醐天皇と相次いで朝廷の帰依を受け、建武元年(1334年)には後醍醐天皇から、大徳寺を京都五山のさらに上位に位置づけるとする綸旨が発せられました。
しかし、足利尊氏によって、後醍醐天皇が吉野に追われ、室町時代になると、大徳寺は幕府から疎んじられ、五山十刹から除かれ、在野的立場にある「林下」の道を歩むことになります。また応仁の乱で伽藍を焼失し、荒廃をしてしまいます。
中興の祖となったのがあの一休和尚(一休宗純)でした。南北朝の動乱が終結したときの北朝の天皇は後小松天皇でしたが、一休宗純は後小松天皇の後落胤といわれています。
一休和尚は、カラスの鳴き声を聞いて、悟りを開いたといわれますが、飲酒・肉食を行なったり、朱鞘の木刀を差して変な格好で街を歩きまわる、正月にドクロを掲げるなど、奇行も多い人物でした。それらの奇行は禅の精神を基に、当時の風習を批判したものとも言われます。
それ故に庶民の人気は高く、応仁の乱の後、後土御門天皇の勅命により大徳寺の住持(第47代)に任ぜられ、酬恩庵(一休寺)から、大徳寺に通うことになります。

一休に帰依していた人物は、能の金春禅竹(こんぱるぜんちく)や茶道創始者の村田珠光などがいました。一休が住持になったことで、堺の豪商はじめ、貴族、大名、商人、文化人など、幅広い層の保護や支持を受け、塔頭が寄進されたことによって、現在の大徳寺があります。大徳寺は茶の湯の世界と縁が深く、武野紹鴎、千利休、小堀遠州をはじめ多くの茶人が大徳寺と関わり、国宝の密庵(みったん)などすぐれた茶室も多く残されています。
京の人々からは「東福寺の伽藍面」「妙心寺の算盤面」「建仁寺の学問面」などと並んで「大徳寺の茶面(ちゃづら)」といわれました。
本能寺の変ののちには、豊臣秀吉が織田信長の葬儀を営み、総見院を建立、併せて寺領を寄進しました。以後、名だたる戦国武将たちがこぞって、塔頭を建立して隆盛を極めるにいたります。
江戸時代初めになると幕府の統制を受け、漬物のたくあんの考案者とも言われる名僧、沢庵宗彭が紫衣事件と呼ばれる流罪の圧迫を受けましたが、三代将軍家光が沢庵に帰依するなど幕府との関係ものちに回復したといわれます。その後、寺運は栄え今日に至っています。
大徳寺は、ご存知、臨済宗大徳寺派大本山です。山号を龍寶山(りゅうほうざん)といい、本尊は釈迦如来、鎌倉時代末期に大燈国師・宗峰妙超が開創しました。宗峰妙超は悟りを開いたあと20年間も五条河原で乞食行を続けたといいます。
花園天皇、後醍醐天皇と相次いで朝廷の帰依を受け、建武元年(1334年)には後醍醐天皇から、大徳寺を京都五山のさらに上位に位置づけるとする綸旨が発せられました。
しかし、足利尊氏によって、後醍醐天皇が吉野に追われ、室町時代になると、大徳寺は幕府から疎んじられ、五山十刹から除かれ、在野的立場にある「林下」の道を歩むことになります。また応仁の乱で伽藍を焼失し、荒廃をしてしまいます。
中興の祖となったのがあの一休和尚(一休宗純)でした。南北朝の動乱が終結したときの北朝の天皇は後小松天皇でしたが、一休宗純は後小松天皇の後落胤といわれています。
一休和尚は、カラスの鳴き声を聞いて、悟りを開いたといわれますが、飲酒・肉食を行なったり、朱鞘の木刀を差して変な格好で街を歩きまわる、正月にドクロを掲げるなど、奇行も多い人物でした。それらの奇行は禅の精神を基に、当時の風習を批判したものとも言われます。
それ故に庶民の人気は高く、応仁の乱の後、後土御門天皇の勅命により大徳寺の住持(第47代)に任ぜられ、酬恩庵(一休寺)から、大徳寺に通うことになります。
一休に帰依していた人物は、能の金春禅竹(こんぱるぜんちく)や茶道創始者の村田珠光などがいました。一休が住持になったことで、堺の豪商はじめ、貴族、大名、商人、文化人など、幅広い層の保護や支持を受け、塔頭が寄進されたことによって、現在の大徳寺があります。大徳寺は茶の湯の世界と縁が深く、武野紹鴎、千利休、小堀遠州をはじめ多くの茶人が大徳寺と関わり、国宝の密庵(みったん)などすぐれた茶室も多く残されています。
京の人々からは「東福寺の伽藍面」「妙心寺の算盤面」「建仁寺の学問面」などと並んで「大徳寺の茶面(ちゃづら)」といわれました。
本能寺の変ののちには、豊臣秀吉が織田信長の葬儀を営み、総見院を建立、併せて寺領を寄進しました。以後、名だたる戦国武将たちがこぞって、塔頭を建立して隆盛を極めるにいたります。
江戸時代初めになると幕府の統制を受け、漬物のたくあんの考案者とも言われる名僧、沢庵宗彭が紫衣事件と呼ばれる流罪の圧迫を受けましたが、三代将軍家光が沢庵に帰依するなど幕府との関係ものちに回復したといわれます。その後、寺運は栄え今日に至っています。
2013年06月28日
伏見の酒と京扇
先日の観光案内は、京の土産処をめぐりました。

では、一件目、大手筋商店街を真ん中あたりにあります、伏見の酒の全蔵元取扱い処「油長」さん。吟醸酒・大吟醸酒・季節のお酒を中心に年間で100種類以上の「伏見の酒」を取り扱っています。店内には「え〜こんなにあるの」と私もガイドを忘れてびっくり!
英勲、玉乃光、招徳、都鶴、月の桂、井筒屋伊兵衛、古都千年うすにごりと吟醸酒やら生原酒などなど。酒好きにはたまらないでしょうね。
なんと店舗には、きき酒カウンターも設置されています。常時80種類以上の伏見の酒が用意されていて、伏見全蔵元のお酒をお猪口単位(150円〜550円)で注文できるのも嬉しい。 じっくりと飲みたい方にはグラス (250円〜1000円)もあります。
二軒目は京扇の老舗ご存知「京扇堂」さんです。

古代中国の故事でいう団扇とは、「うちわ」のことで、折り畳みのできる「扇」は日本ではじめて創られた後、中国にも伝わった我が国起源のもの。
平安時代の初期より、京の都で扇が発明されたといいます。最も古いものとされている扇は、京都東寺の仏像の腕の中から発見された檜扇で元慶元年(879)と記されています。紙扇も平安時代に発明され、これが檜扇とともに中国に伝わり、さらに遠くヨーロッパに広まったのだとか。
京の古い扇屋は 「阿弥」の称号を名乗り、「京扇堂」も旧名は「眞阿弥京扇堂」という名で洛中の人々に親しまれてきました。初代・齊木兵助は、東本願寺の寺侍でしたが、持阿弥で扇の術を得、 天保三年(1832)に西本願寺前の油小路花屋町に店を開いたのが始まりです。
「阿弥」の称号は、平敦盛の妻であった、如仏尼が後嵯峨天皇の皇子・王阿の熱病を扇の風で直したとの伝承に由来します。如仏尼の結んだ庵、御影堂の女人たちが扇を作るようになり、この御影堂を中心にして、多くの扇屋が軒を連ねました。それらの扇屋が、阿弥を称したのだといいます。
では、一件目、大手筋商店街を真ん中あたりにあります、伏見の酒の全蔵元取扱い処「油長」さん。吟醸酒・大吟醸酒・季節のお酒を中心に年間で100種類以上の「伏見の酒」を取り扱っています。店内には「え〜こんなにあるの」と私もガイドを忘れてびっくり!
英勲、玉乃光、招徳、都鶴、月の桂、井筒屋伊兵衛、古都千年うすにごりと吟醸酒やら生原酒などなど。酒好きにはたまらないでしょうね。
なんと店舗には、きき酒カウンターも設置されています。常時80種類以上の伏見の酒が用意されていて、伏見全蔵元のお酒をお猪口単位(150円〜550円)で注文できるのも嬉しい。 じっくりと飲みたい方にはグラス (250円〜1000円)もあります。
二軒目は京扇の老舗ご存知「京扇堂」さんです。
古代中国の故事でいう団扇とは、「うちわ」のことで、折り畳みのできる「扇」は日本ではじめて創られた後、中国にも伝わった我が国起源のもの。
平安時代の初期より、京の都で扇が発明されたといいます。最も古いものとされている扇は、京都東寺の仏像の腕の中から発見された檜扇で元慶元年(879)と記されています。紙扇も平安時代に発明され、これが檜扇とともに中国に伝わり、さらに遠くヨーロッパに広まったのだとか。
京の古い扇屋は 「阿弥」の称号を名乗り、「京扇堂」も旧名は「眞阿弥京扇堂」という名で洛中の人々に親しまれてきました。初代・齊木兵助は、東本願寺の寺侍でしたが、持阿弥で扇の術を得、 天保三年(1832)に西本願寺前の油小路花屋町に店を開いたのが始まりです。
「阿弥」の称号は、平敦盛の妻であった、如仏尼が後嵯峨天皇の皇子・王阿の熱病を扇の風で直したとの伝承に由来します。如仏尼の結んだ庵、御影堂の女人たちが扇を作るようになり、この御影堂を中心にして、多くの扇屋が軒を連ねました。それらの扇屋が、阿弥を称したのだといいます。
2013年06月13日
2013年06月04日
九厘草

これを見られている関係者の皆様ぜひとも広めてくださいね。
写真は下手なのですが、先日、貴船へご案内したときに南丹と市内北部でしか咲いていないという「九厘草』に久しぶりに出会いました。
少しだけ解説をしておくと・・・。
「クリンソウ』は、北海道~本州、四国の山間部に分布する多年草で、サクラソウの仲間です。湿り気のある環境を好み、小川の岸辺などの湿地に自生します。へらの形をした長さ20cmほどの葉を地際から放射状に出し、中心を縦に走る葉脈は白色で太く目立ちます。葉は明るい緑色で表面は少しぼこぼこしており葉脈が細かく入ります。
春になると株の中心から花茎を伸ばし、花茎をぐるりと囲むように同じ高さの場所にサクラソウのような花を数輪咲かせます。 草丈は大きなものでは90cmほどになり、サクラソウの中ではもっとも大型の部類になります。 花色は濃い紅紫色です。(kinta)