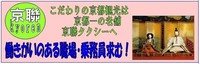2012年03月23日
清凉寺
清凉寺境内でも梅が満開でした。
清凉寺は、嵯峨にある浄土宗の寺院で、山号を五台山と称します。嵯峨釈迦堂といった方が、みなさんご存知かもしれませんね。中世以来「融通念仏の道場」としても知られています。宗派は初め南都六宗のひとつの華厳宗、後に浄土宗となりました。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は奝然(ちょうねん)、開山(初代住職)はその弟子の盛算(じょうさん)です。
この地にはもともと、嵯峨天皇の皇子・左大臣源融(みなもとのとおる)の別荘・栖霞観(せいかかん)がありました。源氏物語に光源氏が造営した「嵯峨のお堂」は、大覚寺の南に所在したとあり、栖霞観の場所と一致します。源融が紫式部『源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの一人といわれる所以です。

浄土宗は通常は阿弥陀如来を本尊とするのですが、釈迦如来がご本尊なのにはいわれがあります。
北インドの釈迦族の王として生まれたゴータマシッタルダは37歳で悟りを開き、お釈迦樣となったと言われます。その時古代インドの王様が栴檀(せんだん)の木で一体の生き写しの釈迦像を造らせました。その後、三世紀から四世紀に掛けて、インド仏教が衰退し、釈迦像は追われるようにシルクロードを通って中国長安に運ばれ、中国大陸を転々としました。
北宋の時代、日本から中国に渡り、五台山(一名、清凉山)を巡礼した東大寺出身の僧・奝然(ちょうねん)がこの仏像に出会います。生き写しの仏像に魅入られた奝然は、この釈迦像を仏師に模刻させました。これが「三国伝来の釈迦像」です。
奝然は、日本に帰国後、京都の愛宕山を中国の五台山に見立て、愛宕山麓にこの釈迦像を安置する寺を建立しようとしました。これは、「都の西北方にそびえる愛宕山麓の地に南都仏教の拠点となる清凉寺を建立することで、相対する都の東北方に位置する比叡山延暦寺と対抗しようとした」と言われています。しかし、その願いを達しないまま奝然は没します。遺志を継いだ弟子の盛算(じょうさん)が棲霞寺の境内に建立したのが、現在の五台山清凉寺なのです。

一方、中国にあった本物の仏像の方は、その後行方がわからなくなってしまい、インドで造られたお釈迦様の像を直接模刻した像はこの清凉寺の像だけとなりました。
通常の釈迦像との違いは、髪がらほつでなく、長い髪の毛を編んでぐるぐる巻いてあり、日本の袈裟と違って全身を衣で被っています。どちらかというとガンダーラの石仏に近いお姿ですね。
さて、昭和の時代になって、この像の胎内からは、造像にまつわる文書、奝然の遺品、仏教版画などの「納入品」が発見されました。これらも像とともに国宝に指定されています。中でも「五臓六腑」(絹製の内臓の模型)は、世界最古の人体模型として、医学史の資料としても注目されています。

境内には何故か豊臣秀頼の首塚があります。住職さんにお伺いすると、昭和55年に大阪城三の丸跡から豊臣秀頼の首と見られる頭蓋骨が発見され、秀頼ゆかりの嵯峨清涼寺では、首塚を造って納め、368年ぶりに安らかな眠りにつかせることになったといいます。この頭蓋骨は、20~25歳の若武者で、首に介錯の跡があり、左耳が不自由だったこと、発掘当時、頭蓋骨の周囲にシジミやタニシの生貝が敷かれ、人為的に埋葬されていること、出土品などから、大阪夏の陣と時期が合致し、豊臣秀頼の首と断定されたといいます。

さて、この地は、平安時代に閻魔大王に仕えたとされる小野篁が六道珍皇寺の井戸から地獄に入り、出てきた場所とされる福生寺の跡地でもあり、生の六道と言われます。境内には福生寺跡の石碑があります。
清凉寺は、嵯峨にある浄土宗の寺院で、山号を五台山と称します。嵯峨釈迦堂といった方が、みなさんご存知かもしれませんね。中世以来「融通念仏の道場」としても知られています。宗派は初め南都六宗のひとつの華厳宗、後に浄土宗となりました。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は奝然(ちょうねん)、開山(初代住職)はその弟子の盛算(じょうさん)です。
この地にはもともと、嵯峨天皇の皇子・左大臣源融(みなもとのとおる)の別荘・栖霞観(せいかかん)がありました。源氏物語に光源氏が造営した「嵯峨のお堂」は、大覚寺の南に所在したとあり、栖霞観の場所と一致します。源融が紫式部『源氏物語』の主人公光源氏の実在モデルの一人といわれる所以です。

浄土宗は通常は阿弥陀如来を本尊とするのですが、釈迦如来がご本尊なのにはいわれがあります。
北インドの釈迦族の王として生まれたゴータマシッタルダは37歳で悟りを開き、お釈迦樣となったと言われます。その時古代インドの王様が栴檀(せんだん)の木で一体の生き写しの釈迦像を造らせました。その後、三世紀から四世紀に掛けて、インド仏教が衰退し、釈迦像は追われるようにシルクロードを通って中国長安に運ばれ、中国大陸を転々としました。
北宋の時代、日本から中国に渡り、五台山(一名、清凉山)を巡礼した東大寺出身の僧・奝然(ちょうねん)がこの仏像に出会います。生き写しの仏像に魅入られた奝然は、この釈迦像を仏師に模刻させました。これが「三国伝来の釈迦像」です。
奝然は、日本に帰国後、京都の愛宕山を中国の五台山に見立て、愛宕山麓にこの釈迦像を安置する寺を建立しようとしました。これは、「都の西北方にそびえる愛宕山麓の地に南都仏教の拠点となる清凉寺を建立することで、相対する都の東北方に位置する比叡山延暦寺と対抗しようとした」と言われています。しかし、その願いを達しないまま奝然は没します。遺志を継いだ弟子の盛算(じょうさん)が棲霞寺の境内に建立したのが、現在の五台山清凉寺なのです。

一方、中国にあった本物の仏像の方は、その後行方がわからなくなってしまい、インドで造られたお釈迦様の像を直接模刻した像はこの清凉寺の像だけとなりました。
通常の釈迦像との違いは、髪がらほつでなく、長い髪の毛を編んでぐるぐる巻いてあり、日本の袈裟と違って全身を衣で被っています。どちらかというとガンダーラの石仏に近いお姿ですね。
さて、昭和の時代になって、この像の胎内からは、造像にまつわる文書、奝然の遺品、仏教版画などの「納入品」が発見されました。これらも像とともに国宝に指定されています。中でも「五臓六腑」(絹製の内臓の模型)は、世界最古の人体模型として、医学史の資料としても注目されています。

境内には何故か豊臣秀頼の首塚があります。住職さんにお伺いすると、昭和55年に大阪城三の丸跡から豊臣秀頼の首と見られる頭蓋骨が発見され、秀頼ゆかりの嵯峨清涼寺では、首塚を造って納め、368年ぶりに安らかな眠りにつかせることになったといいます。この頭蓋骨は、20~25歳の若武者で、首に介錯の跡があり、左耳が不自由だったこと、発掘当時、頭蓋骨の周囲にシジミやタニシの生貝が敷かれ、人為的に埋葬されていること、出土品などから、大阪夏の陣と時期が合致し、豊臣秀頼の首と断定されたといいます。

さて、この地は、平安時代に閻魔大王に仕えたとされる小野篁が六道珍皇寺の井戸から地獄に入り、出てきた場所とされる福生寺の跡地でもあり、生の六道と言われます。境内には福生寺跡の石碑があります。
Posted by 京聯自動車観光部 篠田ほつう at 10:03│Comments(0)
│篠ちゃんの京都時空観光案内
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。